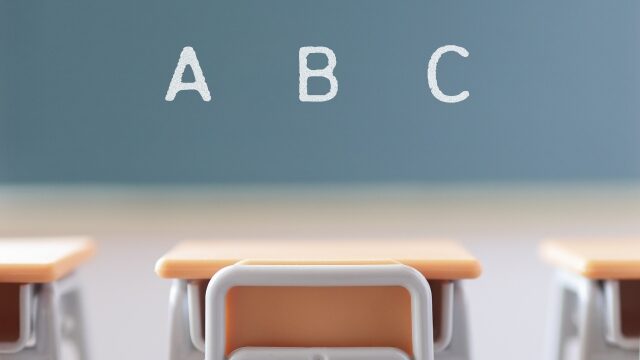先日からNHKで「お別れホスピタル」なるドラマがはじまった。
タイトルだけなら見なかったと思うが、最近注目している「岸井ゆきの」さんが出演とのことで、録画の予約もした。
まだ1話して見ていないが、きっと最後まで見届けると思う。
さて。
この番組の中で、隠れてタバコを吸う患者さんがいて、それをたしなめる看護師さんがいて。
今の嫌煙ブームもあり、喫煙場所がないこともあるが、なにより患者さんの身体の心配がある。
患者さんは一旦タバコを消すが、タバコの習慣はなかなか諦めることなどできない。
私自身が昔むかし喫煙者だったので(30年以上前のこと)、タバコを取り上げられるせつなさはよくわかる。
今では、嫌煙者の仲間入りであるが。
決して褒められる部分の多くない私の人生の中で、唯一良かったことは禁煙が出来たことかもしれない。

煙草であるが、私の母も喫煙者だった。愛煙家だった。
45歳で亡くなってしまったが、最期まで煙草をやめることはなかった。
ついでに言えば、酒飲みでもあった。
中酒飲みといったところか。本人は大酒を飲みたかったと思うが、体質が多分アルコールに強くなくて、少し飲んではすぐに眠ってしまう酒だ。
そのかわり、起きている間は飲んでいる。
アルコールに弱い体質は、多分私も遺伝でもっている。
存命であれば、もう90歳を超えているが、この年齢のご婦人で喫煙者はとても珍しかった。
お酒も同様に。
ついでの話であるが、母の母、私の祖母も喫煙者だった。
祖母は紙巻きタバコではなく、キセルで刻み煙草を吸っていた。

一度につめた煙草はほんの数回しか吸い込むことがなく、すぐにポンポンと茶殻入れのような物にその種火を落とし、次の葉っぱをつめて、落とした種火から火をもらってまた吸っていた。
必ず2回詰める作業をしていた。2回以上続くことはなかった。
チマチマしたことが好きだった私は、祖母が目を離した隙を狙って、このキセルの「ヤニ」をほじって掃除をした。
どうも、通気が悪くなるようで、その度に祖母から「余計なことをするな」と怒られた。
若い時から高血圧で、40代のはじめで倒れたこともある母親は、お酒も煙草も医者からは止めるように指導を受けていたが、ついに止めることはなかった。
アウトローで自分の主義主張が正しい、他は排除するという母は誰の指示も受けない。
夫婦二人で酒飲みなので、父が止めることもなかった。
唯一、子どもである私の目だけは気になったようで、私の前では湯呑茶わんで焼酎を飲んで、外面をごまかしてはいた。
自分で依存症であるという自覚は持っていたようだ。
そんな母が倒れて入院をした。
次に倒れた時にはまずいという事は前回から言われていたし、重症だった。
脳が詰まっているという説明だったから、脳梗塞だったのか…と、今は思う。
母は、最後の病院で13日間を生きた。

意識不明になったのは、最期の日の数時間だけで、それ以外は意識はあった。
しかし、13日間のうち、通常の鮮明な意識は1日しかなかった。
それ以外は、少し歩くことはできても、自分のことも出来なくなっていた。
自分の存在もわからない状態だったのだと思う。
洗い場で、母の洗濯物を手洗いしている時に、廊下を無意味に歩く母を見つけて、子どものくせに、軽く叱ってベットに戻した時の事を鮮明に思い出す。
もう正気ではなかった母親を、高校生の私は正直イヤだった。
こんな事がいつまで続くのかと思ったのは、母の身体がまだ動いたからだろう。
実際に、昏睡をした時は、その事が現実に思えなかった。
たった一日の意識の鮮明な日は、完全な「仲直り現象」だったのだろう。
炭鉱のマチだったので、母が最後を過ごしたのは炭鉱病院だった。
割と大きな病院で、母はそこの第三病棟で過ごした。
4~6人の部屋をカーテンで仕切るのではなく、老若男女入り乱れた数十人の相部屋でカーテンの仕切りが個別にあった。
現在とは違って、比較的オープンで、昼間にカーテンの仕切りをしている人は少なかったから、広い部屋にたくさんの人がうごめいているような状況だった。
母はその広い部屋の、入り口すぐだった記憶がある。

母はもう、仲直りの一日を除いて、普段の母ではなかった。
ほぼ認知症のような状態になっていた。
ある時、そんなカーテンで仕切った病室の机の引き出しの中と、下の開き戸の中に煙草とお酒の小瓶を見つけた。
驚いた。
どうしてここに煙草とお酒があるのか。母に聞いても要領を得ない。
吸ったか、飲んだか。それはわからない。
現代とは違って、病室内でお酒は飲めないが煙草は吸えた時代。
結局、何故そこに煙草とお酒があったのかは、真相はわからなかった。(売店がないから買うことはできないし、母はお金を持っていない)

入手経路がわからないから、防ぎようもなかったが、それはダメだと注意だけはしつこくして、私たちは帰宅をした。
それでも、翌日か翌々日にまたお酒が開き戸の中にあった時にはガッカリした。
恐らく、煙草はもう吸えなかったと思う。火をつけることが出来なかったと思う。
しかし、お酒は飲んだかな…? と、思う。
今にして思えば、湯呑でごまかして、ほんの少しなら飲んでも良かったかな、と思ったりもする。当時はそんな事、思いもしなかったが。
母も数日後に死ぬことがわかっていたら、何が何でも飲みたかっただろう。
「お別れホスピタル」の患者さんは、自分の煙草を吸っていた。
持ってくることも、買うことも出来た。
母は持ってくることも、買うことも出来なかった。
母はどうやって、あの煙草とお酒を手に入れたのだろう。
ぼんやり徘徊をするだけで、話す事さえ出来なかった。
煙草を吸っている他の患者さんのもとに行って、欲しいと言ったのだろうか。
欲しそうに見る母に、誰かが持たせてくれたのだろうか。
悪いと知りながら、お酒の瓶を持たせたのだろうか。
誰が、どんな思いで関わってくれたのだろうか。
誰が。どうやって。
もう50年も前のこんな小さな出来事。
思い出すことはあっても、今まで深く考えたこともなかった。
今になって、真相が知りたい。
もう絶対に知りようもないけれど。